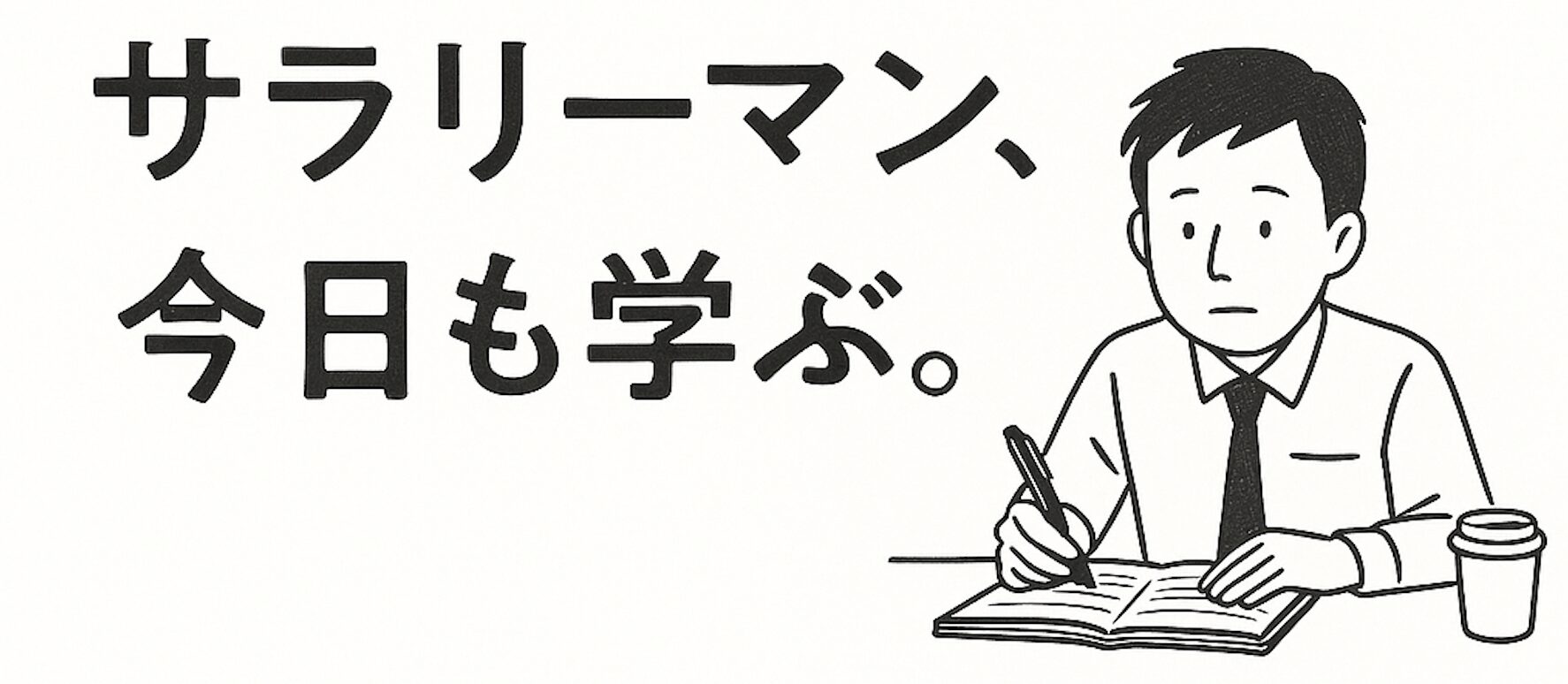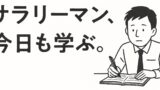最近、我が社(JTC)でもDXの波が押し寄せてきており、「これからはデータの時代だ!」「実験計画法(DOE)で全てが解決する!」と、まるで新興宗教のような熱量で上層部がDOE信仰を唱え始めている。確かにDOEは素晴らしい。統計的に有意差を見極め、無駄な試行回数を削減できる。理にかなっている。理屈はわかる。
でもね、言わせてもらえば、万能じゃないんですよね、DOEは。
最近では、どんな相談をしても「DOEでやったの?これDOE回してみようか」と返ってくる。「妻の機嫌が悪くて…」「DOEで妻が不機嫌になる原因を特定しよう」「子どもが夜寝なくて…」「2水準3因子の直交表で分析してみたら?」——いやいや、DOEって夫婦関係、育児にも効くのかとツッコミたくなる日々である。(流石にこれはジョークだけど。)
上から「とにかくDOE!」「何でもDOE!」と命じられるが、DOEだって人を選ぶ。適切な要因を選び、交互作用を見極め、現場の実情を踏まえて設計しないと、ただの時間と試薬の浪費装置になる。しかもやってみたら、「因子が多すぎて解釈不能」「再現性が怪しい」「そもそも仮説がない」と、天下のDOE様も匙を投げる結果に。
なのに、DOEを使えば自動的にイノベーションが起きると信じている人々は、何か新しい宗教の開祖か何かだろうか。いや、それとも「他社もやってるからうちも」という、お決まりの“横並び精神”の申し子か。これだから、会社の離職率も年々あがるわけだ。
現場としては「目的に応じて手法を選ぼう」というごく真っ当な提案をしても、「なぜやらない?」と、話が通じない。“DOE教の教義に背く者、すなわち異端”という扱いだ。生まれる時代を間違えていたら、拷問の上殺されていただろう。「チ。」のように。
誤解のないように言っておくと、DOEを否定しているわけではない。私は統計学や実験計画法という学問は好きである。正しく使えば強力な武器になる。でも、ハサミは紙を切るものであって、スープをすくう道具じゃない。それと同じで、DOEも「向き・不向き」があるのだ。
本当に大事なのは、ツールの使い方ではなく、何を解決したいのかという問い。その問いがあって初めて、DOEも機械学習も意味を持つ。逆にいえば、問いが曖昧なら、どんな高尚な手法も、ただの「それっぽいグラフを出すマシン」に過ぎない。
「DOEやったか?」と問われる日々だが、心の中ではこうつぶやいている——
「うん、やったよ。妻とのいざこざも、育児の悩みも、背中にできたニキビも全部DOEで解決よ。(ヤケクソ)」
(所有時間25分)